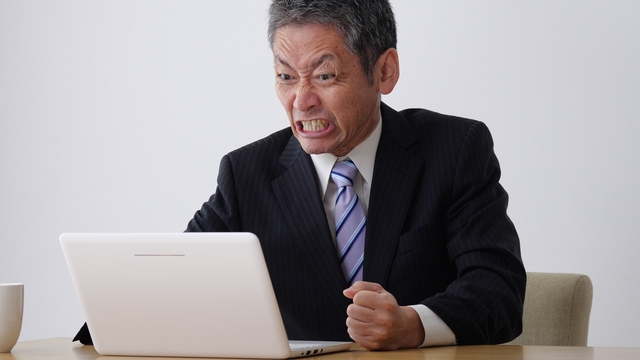本来であれば熱しやすく冷めやすいはずの「無思考型いじめ」が、加害者の身勝手な思い込みと結びつくことで継続的ないじめに変貌する仕組みと、その対処法について詳しく解説します。
目次
無思考型いじめとは?定義と特徴を理解する
無思考型いじめとは、加害者が自身のこだわりポイントに触れられた際に、理性的な判断を欠いたまま他者を攻撃する行為です。通常は衝動性が強く、考える間もなく攻撃的な行動に出る特徴があります。感情が論理的思考よりも先行し、本来であれば熱しやすく冷めやすい短期集中型の傾向を示します。
しかし、本来は一時的な攻撃で終わるはずの無思考型いじめが、加害者の身勝手な思い込みと結びつくことで、長期化・深刻化するケースが急増しています。これが現在の教育現場で大きな問題となっているのです。
「馬鹿にされた」という思い込みが生むいじめの連鎖
加害者のこだわりポイントが自己アイデンティティと密接に関連している場合、非常に危険な思考回路が生まれます。こだわりが通らないことを自分が否定されたと解釈し、それを馬鹿にされたと受け取り、許せないという感情から継続的な攻撃に発展するのです。
最も重要なのは、相手に馬鹿にする意図がなくても、加害者が一方的に「馬鹿にされた」と判断してしまうことです。この主観的な解釈が、いじめの正当化理由として機能してしまいます。自分を基準とした身勝手な思い込みが、長期間にわたる陰湿ないじめの温床となっているのです。
教師間いじめの具体的事例と分析
飲み会での権力誇示型いじめ
職場の飲み会で先輩教師がお酒を勧める場面を想像してください。後輩教師が健康上の理由で断ったり、自らお酌に行かなかったりした場合、「俺の酒が飲めないのか」と激高する先輩がいます。これは権威の否定と解釈され、「なめている」という被害妄想から継続的な嫌がらせが始まるパターンです。
このタイプの加害者は、アルコールを介した上下関係の確認で自己存在価値を測定する傾向があります。現代のハラスメント意識の高まりにより、従来の権力構造が通用しなくなったことへの反発も要因の一つといえるでしょう。酒の席で自分の意のままに状況が動くことで存在感を示してきた人が、それを否定されたと感じた時の怒りは相当なものです。
職場恋愛のもつれから生じるいじめ
教師も人間である以上、職場での恋愛感情が生まれることは自然なことです。しかし、その恋愛が成就しなかった場合、問題が発生することがあります。振られた側が元恋愛対象への直接的な嫌がらせを始め、さらにその人が他の同僚と交際を始めると、新しいパートナーへも攻撃が拡大されるのです。
最終的には職務上必要なコミュニケーションすら意図的に遮断するようになります。プライベートな感情と職務を完全に混同し、自己の恋愛的価値観を否定されたことへの過剰反応が、職場全体の雰囲気を悪化させていきます。職場における人間関係の閉鎖性も、この問題を深刻化させる要因となっています。
公私混同がもたらす職場環境の悪化
無思考型いじめが継続化すると、必要な連絡事項の意図的な遮断、会議や研修での協力関係の破綻、チームワークを要する教育活動への悪影響など、業務レベルでの深刻な障害が発生します。これらの問題は他の教職員にも萎縮効果をもたらし、学校全体の雰囲気を悪化させ、最終的には教育の質の低下につながります。
教師という立場でありながら人権侵害行為であるいじめを行うことは、教育公務員としての職務倫理違反であり、児童・生徒への悪影響も計り知れません。社会的信頼の失墜は、学校という組織全体の存在意義を問われる事態にもなりかねないのです。
効果的な初期対応戦略:管理職の役割
管理職には早期発見のためのシステム構築が求められます。職員室での不自然な人間関係、業務連絡の滞りや回避行動、会議や行事での協力関係の変化などを注意深く観察する必要があります。定期的な個人面談の実施、匿名での相談窓口の設置、第三者による客観的観察などの情報収集の仕組みも重要です。
対応は段階的に進める必要があります。まず複数の情報源からの聞き取り、具体的な行動の記録収集、当事者双方からの事情聴取による事実確認を行います。次に口頭での注意・指導、行動改善の具体的要求、継続的な監視体制の構築による初期介入を実施します。改善が見られない場合は文書による警告、人事評価への反映、必要に応じた配置転換などの正式処分に移行します。
周囲の教職員ができる支援策
直接的な介入が困難な場合でも、できることは数多くあります。パソコンで作成した匿名メモを管理職に提出する、外部相談窓口に通報する、教育委員会に情報提供するなど、匿名での情報提供は効果的な手段です。筆跡が判別されないよう配慮すれば、身元を明かすことなく問題提起が可能です。
被害者への間接的支援も重要です。孤立させない環境作り、業務上のフォローや精神的な支えとなる関係性の構築により、被害者の心理的負担を軽減できます。同時に、日時と場所の詳細、具体的な言動の内容、目撃者の有無、被害者の反応や状態などの証拠収集と記録も欠かせません。客観的事実のみを記載し、感情的な表現を避けた継続的な記録の蓄積が、後の対応において重要な資料となります。
根本的な解決策:なぜいじめが起こるのかを考える
ハラスメント研修を何度やっても、人事ローテーションをしても、いじめはなくならない。なぜか。
答えは簡単です。いじめをする人間の根本的な問題に手をつけていないからです。
「俺の酒が飲めないのか」と激高する教師は、研修を受けたところで変わりません。むしろ「最近はうるさいから表に出さないようにしよう」と陰湿化するだけです。恋愛がうまくいかなかった途端に職場でいじめを始める人間も同様です。公私の区別がついていない大人が、システムで変わるはずがありません。
本当に必要なのは個人の問題として扱うことです。いじめをする教師は、教師としての適性に根本的な欠陥があります。子どもにいじめはダメだと教える立場の人間が、自分はいじめをしているのです。この矛盾に気づかない人間が教壇に立っていることこそが最大の問題なのです。
まとめ:きれいごとでは解決しない現実
「組織全体で取り組みましょう」「意識改革が大切です」「継続的な努力を」。こうした呼びかけを何年続けても、教師間のいじめは減っていません。
現実を見てください。いじめをする教師は、する。しない教師は、しない。それだけです。
できることは二つだけです。一つは、被害者を守ること。具体的には証拠を集めて管理職に報告する、必要なら外部に通報する、被害者を孤立させない。もう一つは、加害者を排除すること。口頭注意程度では何も変わりません。人事評価に反映させ、最終的には現場から離れてもらう以外に方法はないのです。
いじめをする大人が変わることを期待するのは時間の無駄です。そんな人間から子どもたちを、そして同僚を守ることだけを考えましょう。