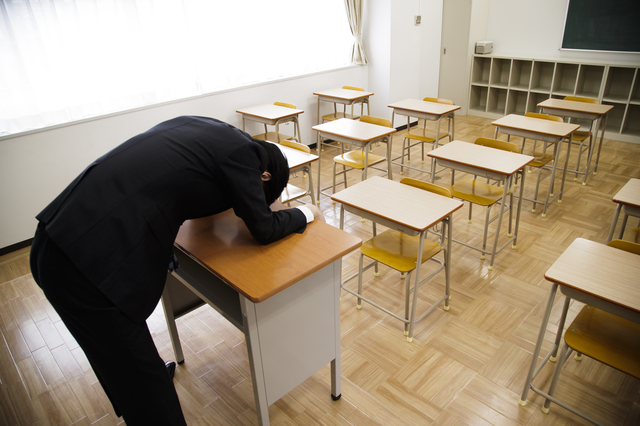現在、日本の教育現場では深刻な問題が進行しています。文部科学省の調査によると、精神疾患による教職員の病気休職者数は年間約6500人を超え(令和4年度)、その多くがうつ病やうつ状態によるものです。しかし、より深刻なのは復職の過程で起こる問題です。
教師のうつ病復帰における最後の関門、それが復帰プログラムです。しかし現実には、このプログラムこそが復帰を阻む最大の障害となっています。管理職や教育庁職員、医師の監視下で行われる授業参観は、まさにうつ病を発症したその場での再現訓練です。当事者にとっては地獄のような体験となります。
なお、その惨状を書いた記事は、こちらをご覧ください。
〈「うつ」で休職した先生が復帰する場所は?〉
目次
教育現場の構造的問題:なぜ教職員が精神疾患を患うのか
過重労働と責任の重圧
現代の教職員が置かれている環境は、かつてないほど過酷です。授業準備、生徒指導、保護者対応、部活動指導、各種行事の企画・運営、膨大な事務作業。これらすべてを限られた時間の中でこなさなければなりません。
さらに深刻なのは、社会からの期待とプレッシャーの増大です。「教師は聖職」という古い概念が残る一方で、現実的な支援体制は整備されていません。保護者からのクレーム、管理職からの圧力、同僚との人間関係、生徒の問題行動への対応。これらが複合的に重なり合い、真面目で責任感の強い教職員ほど心を病むという皮肉な現象が起きています。
孤立する教職員たち
教育現場では「個人主義」が根強く、困っている教職員への組織的サポートが不十分です。「自分のクラスは自分で何とかする」という風潮の中で、助けを求めることすら困難な状況が生まれています。同僚に相談すれば「弱い教師」のレッテルを貼られ、管理職に報告すれば評価に響きます。このような環境では、問題が深刻化するまで誰も気づかない、あるいは気づいていても見て見ぬふりをするという悪循環が続きます。
特に新任教師や転勤したばかりの教職員は、その学校の「暗黙のルール」や人間関係を把握するだけでも大きなストレスとなります。本来であれば先輩教師がメンターとして支援すべきところが、皆が自分の業務で精一杯という状況では、新人を育てる余裕すらありません。
真面目な教職員ほど追い詰められる残酷な現実
責任感が生む自己破壊のスパイラル
精神疾患を患った教職員の多くは、もともと責任感が強く真面目な性格の持ち主です。生徒のため、保護者のため、学校のためを思い、自分を犠牲にしてでも職務を全うしようとします。しかし、この「献身的な姿勢」こそが、彼らを病気へと追い込む要因となっています。
「もっと頑張らなければ」「期待に応えなければ」「迷惑をかけてはいけない」。こうした強迫的な責任感は、適切な休息や自己ケアを妨げ、心身の限界を超えた働き方を常態化させます。そして、いざ体調を崩したときには、「自分が弱いから」「能力が足りないから」と自分を責める思考パターンに陥ってしまいます。
復帰プログラムが生む二次被害
そんな彼らが復帰プログラムで直面するのは、「できない自分」との向き合いです。通常よりも自責の念が強い精神疾患の患者にとって、これほど残酷なことはありません。
復帰プログラムでは、管理職、指導主事、産業医などが授業を参観し、「復帰可能かどうか」を判定します。この状況は、まさに病気になる直前の「評価される恐怖」「完璧でなければならないプレッシャー」を再現しています。本人にとっては、病気の原因となったストレス状況に再び身を置くことを意味するのです。
完治していない寛解状態で臨む復帰プログラムにおいて、少しでも「うまくいかない」ことがあれば、それは即座に自己否定へとつながります。「やっぱり自分はだめだ」「復帰なんてできるわけがない」「みんなに迷惑をかけている」。せっかく回復の兆しを見せていた症状が、このプログラムによって再び悪化してしまうケースは決して珍しくありません。
評価する側の認識不足
問題は、評価する側の多くが精神疾患に対する正しい理解を持っていないことです。「見た目は普通だから大丈夫だろう」「以前はできていたのだから、今もできるはず」という誤った判断が、当事者をさらに追い詰めます。
精神疾患の回復は、身体的な病気とは異なり、波があり、予測困難な側面があります。今日調子が良くても、明日は起き上がることすら困難かもしれません。このような疾患の特性を理解せずに、一律の基準で評価することは、科学的にも人道的にも適切ではありません。
管理職が見落とす教育現場の矛盾
ダブルスタンダードの実態
ここで考えてみてください。果たして全ての教職員が「通常の授業」を行っているでしょうか。残念ながら答えはノーです。職責を果たさず、管理職の注意を無視し、時には暴言すら吐く教職員が存在するのも現実です。授業準備を怠り、生徒指導を放棄し、同僚との協調性を欠く者もいます。
しかし、そのような問題のある教職員に対しては、なぜか寛大な対応が取られることが多いのです。「あの人はああいう人だから」「昔からそうだから仕方ない」という理由で、事実上放置されているケースも珍しくありません。
一方で、病気から復帰しようとする真面目な教職員には、完璧な授業運営、完璧な生徒指導、完璧な事務処理が求められます。この明らかなダブルスタンダードこそが、弱者いじめの構造を生み出しているのです。
能力主義の罠
多くの正直者である教職員が馬鹿を見る現状の中で、最も支援が必要な人たちが最も厳しく評価されます。これが今の復帰プログラムの実態です。
「能力があるから厳しく評価される」「期待されているから要求水準が高い」という論理は一見もっともらしく聞こえますが、病気から回復しようとする人に対してこの論理を適用することは適切ではありません。回復期にある人には、まず安心できる環境と適切なサポートが必要であり、高い要求水準は逆効果になることが多いのです。
組織防衛の論理
管理職の立場から見れば、復帰プログラムを厳格に実施することで「責任を果たしている」という姿勢を示すことができます。万が一、復帰後に問題が生じた場合でも、「適切な手順を踏んだ」という免罪符を得ることができます。
しかし、この組織防衛の論理が、当事者の回復を最優先にすべき復帰支援の目的を歪めています。本来であれば、一人ひとりの教職員の状況に応じた個別的な支援が必要であるにもかかわらず、画一的で官僚的な手続きが優先されてしまうのです。
50キロしか持てない人に80キロを要求する愚かさ
個別性を無視した一律要求
復帰プログラムの根本的な問題は、対象となる教職員の現状を無視した一方的な要求にあります。100メートルを12秒台でしか走れない人に11秒台を要求し、50キロのバーベルしか持ち上げられない人に70キロ、80キロを求める。これと同じことが教育現場で行われています。
精神疾患からの回復は、人それぞれ異なるペースで進みます。ある人は3ヶ月で職場復帰できるかもしれませんが、別の人は1年以上かかるかもしれません。同じ人でも、症状の種類や重症度、治療の経過、家庭環境、職場環境などによって、復帰に要する時間は大きく変わります。
しかし、現在の復帰プログラムは、このような個別性を十分に考慮していません。教育委員会の年間スケジュールや人事異動の都合が優先され、当事者の回復状況は二の次になってしまうことが多いのです。
段階的復帰の重要性
指示を出す側の一方的なペースや考えによって、言われた側が潰れていく様子を、私たちは何度も目の当たりにしてきました。本来であれば、その人ができることから少しずつ負荷をかけていくのが当然のはずです。
リハビリテーションの基本原則は、現在の能力を正確に把握し、そこから段階的に負荷を増やしていくことです。これは身体的なリハビリでも精神的なリハビリでも同じです。急激な負荷の増加は、回復を遅らせるだけでなく、症状の悪化を招く危険性があります。
失敗体験の積み重ねが生む悪循環
無理な要求を続けることで、当事者は「また失敗した」「やっぱりできない」という失敗体験を積み重ねることになります。これらの失敗体験は、自己効力感を著しく低下させ、「自分は価値のない人間だ」「職場に戻る資格がない」という否定的な思考を強化してしまいます。
一度この悪循環に陥ると、そこから抜け出すのは非常に困難になります。本来であれば小さな成功体験の積み重ねによって自信を回復すべき時期に、失敗体験を重ねてしまうことで、回復が大幅に遅れてしまいます。
真の回復を待つ勇気
責任感と罪悪感の呪縛
精神疾患からの復帰を急ぐ教職員の多くは、「早く復帰しないと迷惑がかかる」という責任感や罪悪感に駆られています。「自分のせいでクラスの子どもたちに迷惑をかけている」「同僚に負担をかけて申し訳ない」「保護者からどう思われているか心配だ」。
このような思いは、教職員としての使命感から生まれる自然な感情ですが、同時に回復を妨げる要因にもなっています。焦りや不安が症状を悪化させ、結果として復帰をさらに困難にしてしまいます。
無理な復帰が招く二次被害
しかし、まだ寛解にも至っていない状態での無理な復帰は、結果として周囲により大きな迷惑をかけることになりかねません。授業中に体調を崩したり、生徒指導で適切な判断ができなかったり、同僚とのコミュニケーションがうまく取れなかったりする可能性があります。
最悪の場合、復帰後すぐに再び休職に追い込まれることもあります。このような「回転ドア現象」は、当事者にとって大きなトラウマとなるだけでなく、職場全体の士気にも悪影響を与えます。
管理職の責任と判断力
管理職には、教職員の表情や発言、身体の状態を注意深く観察し、適切な判断を下す責任があります。医師の診断書や復帰プログラムの結果だけでなく、日常的な様子から回復状況を見極める洞察力が求められます。
もし無理な状態だと判断したなら、「今はゆっくりと休んでください。あなたがより元気な状態で戻ってくださることが私たちの願いです。職場のことは心配いりません。その時間は、あなたにも私たちにも必要な時間なのです」と、温かい言葉をかけることが何より大切です。
このような言葉は、当事者の罪悪感を和らげ、安心して治療に専念できる環境を提供します。短期的には人員不足などの問題が生じるかもしれませんが、長期的に見れば、健康で意欲的な教職員が職場に戻ってくることで、より良い教育環境が実現されます。
支援の姿勢で臨む復帰プログラム
段階的復帰の具体的実践
本当に前向きな気持ちで復帰を希望する教職員には、その意欲を全力で支援すべきです。ただし、月曜日に3コマの授業があるからといって、いきなり3コマ全てを完璧にこなすことを要求する必要はありません。まずは50分の授業から始めればいいのです。
復帰初期は、授業時間を短縮したり、担当クラス数を減らしたり、複雑な教材は避けて基本的な内容に集中したりする配慮が必要です。また、授業以外の業務についても段階的に増やしていきます。
部活動指導では顔を出して指示を出すだけ、分掌業務も複数の担当があっても一つに集中してもらいます。量を減らすことで申し訳なく思う教職員もいますが、「任されている」という実感こそが回復への大きな力となります。分掌を丸ごと外したり、部活動から完全に遠ざけたりする必要はないのです。
成功体験の積み重ね
復帰支援において最も重要なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。「今日は1時間の授業を最後まで集中して行えた」「生徒との会話が楽しかった」「同僚と笑顔で挨拶ができた」。このような些細な成功でも、当事者にとっては大きな意味を持ちます。
管理職や同僚は、これらの成功を見逃さず、適切に評価し、承認することが大切です。「今日の授業、生徒たちが集中していましたね」「○○さんが戻ってきてくれて、職員室が明るくなりました」などの言葉かけは、自己効力感の回復に大きく貢献します。
柔軟性のある支援体制
復帰支援においては、画一的なプログラムではなく、個々の教職員の状況に応じた柔軟な対応が必要です。ある人は午前中の方が調子が良いかもしれませんし、別の人は午後の方が集中できるかもしれません。週に3日の勤務から始める人もいれば、毎日短時間の勤務を希望する人もいるでしょう。
このような多様性を受け入れ、それぞれに最適な復帰プランを作成することが、真の復帰支援となります。そのためには、管理職だけでなく、産業医、スクールカウンセラー、同僚教職員などが連携し、チーム一体となって支援に取り組む必要があります。
真の改革への道筋
システムの根本的見直し
現在の復帰プログラムの問題点を根本的に解決するためには、システム全体の見直しが必要です。評価中心の復帰判定から、支援中心の復帰促進への転換が求められます。
まず、復帰プログラムの目的を明確にすることが重要です。目的は「復帰可能かどうかを判定すること」ではなく、「安全で確実な復帰を支援すること」であるべきです。この目的の転換により、プログラム内容も大きく変わってくるはずです。
専門性の向上
復帰支援に関わる全ての人が、精神疾患に対する正しい知識と理解を身につける必要があります。管理職、指導主事、産業医はもちろんのこと、同僚教職員も含めて、継続的な研修や勉強会を実施することが重要です。
特に、精神疾患の症状の変動や回復過程の特徴、効果的な支援方法、不適切な対応が与える悪影響などについて、科学的根拠に基づいた知識を共有することが必要です。
予防的取り組みの強化
復帰支援と同様に重要なのが、精神疾患の予防です。過重労働の解消、職場環境の改善、ストレス管理の教育、早期発見・早期対応のシステム構築など、包括的な取り組みが必要です。
また、教職員が気軽に相談できる窓口の設置や、メンタルヘルスチェックの定期実施、ピアサポート制度の導入など、予防から復帰まで一貫した支援体制を構築することが重要です。
おわりに:人間らしい教育現場を目指して
教職員の精神疾患とその復帰支援の問題は、単なる個人の問題ではありません。それは、現代の教育現場が抱える構造的な問題の表れであり、教育の質そのものに関わる重要な課題です。
真面目で責任感の強い教職員が心を病み、復帰を阻まれる現状は、教育現場の人間性を失わせ、結果として子どもたちの教育にも悪影響を与えます。私たちが目指すべきは、教職員が安心して働ける環境であり、それは同時に子どもたちが安心して学べる環境でもあります。
復帰プログラムが「復帰不可能プログラム」と呼ばれる現状を変えるためには、一人ひとりの教職員を大切にし、その回復を真摯に支援する姿勢が何より重要です。それは決して特別なことではありません。人として当然の配慮であり、教育に携わる者として持つべき基本的な心構えなのです。
教育現場に人間らしさを取り戻し、教職員が誇りを持って働ける環境を実現すること。それが、真に子どもたちのためになる教育改革の第一歩なのです。