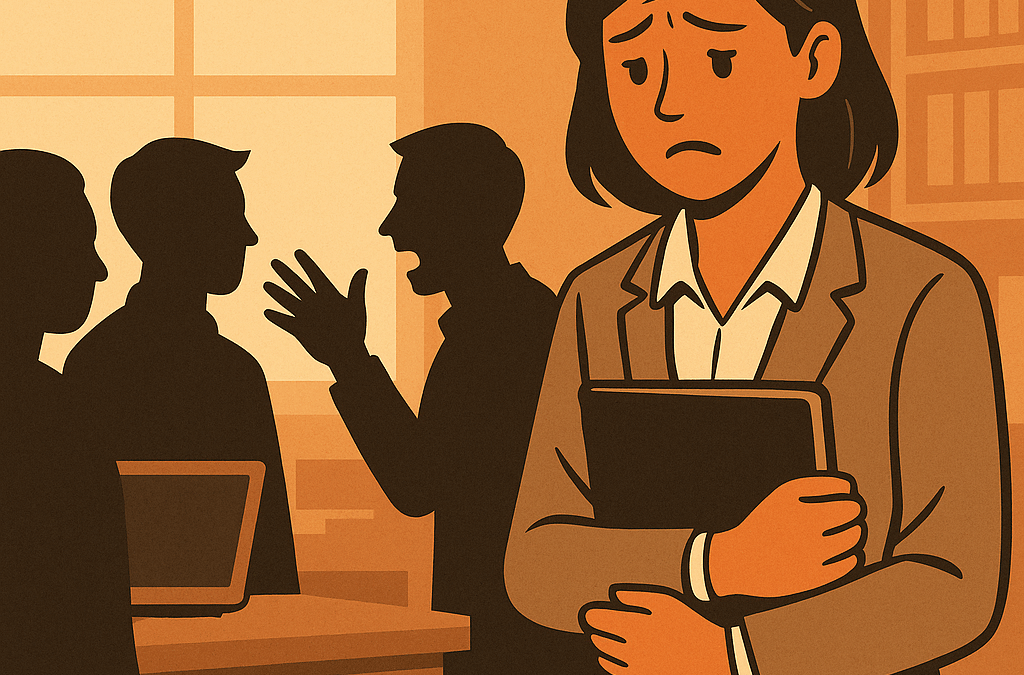あなたは毎朝、職員室のドアの前で一瞬立ち止まるのではないでしょうか。深呼吸して、表情を作って、そしてドアを開ける。その一連の所作が日常になっていないでしょうか。
「今日はまた何を言われるだろう」
「今日は誰の前で批判されるだろう」
「今日はどんな情報から除外されるだろう」
これを読んでいるあなたが、もし今このような毎日を過ごしているなら、まずは一つのことを知ってほしいと思います。あなたは一人ではありません。
教師という崇高な仕事に就きながら、同じ教育者からの理不尽ないじめに苦しむ先生たちは、想像以上に多いのです。7年間カウンセラーとして教師の心に寄り添ってきた私のもとには、繰り返し同じような苦しみを抱えた方々が訪れます。彼らの体験を、あなたに共有したいと思います。
目次
自己愛型いじめとは何か
本題に入る前に、「自己愛型いじめ」について明確にしておく必要があります。「自己愛型いじめ」とは、自己愛が強い加害者が自己の優越感や理想的自己像を維持するために行う、組織的かつ継続的な精神的攻撃のことです。私の造語です。
一般的ないじめと異なる点は、加害者が「自分は正しい」「自分は被害者を助けている」という強固な信念を持っていることです。彼らは自分の行為をいじめとは認識せず、むしろ「指導」「教育的配慮」「組織のため」などと正当化します。
この種のいじめが特に危険なのは、被害者自身が「自分に問題があるのかもしれない」と思い込みやすいことです。自己愛型いじめは、被害者の自己肯定感を徐々に奪い、最終的には心身の健康を著しく損なうことになります。
事例1:管理職からの自己愛的いじめ ― 「指導」という名の支配
Y先生(30代・女性)は15年のキャリアを持つ中学校教師でした。生徒や保護者からの信頼も厚く、同僚からも「子どもの心をつかむのが上手い先生」と評価されていました。
しかし学校生活は4月の人事異動と共に一変します。新しく赴任してきたN教頭(50代・男性)は初日から驚くほどの細かい指示を出しました。
「私の授業をN教頭が参観するようになったのは着任から3日目のことでした。最初は『新任の教頭先生だから学校の様子を知りたいのだろう』と思いました。でも次第にその異常さに気づきました」とY先生は振り返ります。
N教頭は週に3〜4回、必ずY先生の授業を後ろで見学。他の教師の授業参観は月に1回程度なのに対し、明らかに頻度が違いました。そして授業後には必ず「改善点」が指摘されます。
「板書の字が小さい」「発問の間が短すぎる」「教材研究が足りない」…指摘は具体的ながらも、改善しても次は別の点を指摘されるという終わりのない批判の連続でした。
最も辛かったのは、職員会議での公開処刑のような指摘です。
「先日のY先生の研究授業は残念でしたね。ベテランなのにあのレベルでは困ります」
「若手教師の見本になるべきY先生の授業があれでは、学校全体のレベルが下がります」
こうした言葉は他の教師たちの前で、まるで当然のように発せられました。当初は反論していたY先生ですが、次第に「何を言っても無駄」と諦めるようになります。
N教頭の言動には典型的な自己愛的特徴がありました。彼は自分の教育観を絶対視し、それに合わないY先生の指導法を徹底的に否定。さらに「部下思いの熱心な管理職」という自己イメージを崩さないよう、常に「指導」という名目を使いました。
最も悪質だったのは、Y先生が体調を崩して2日間休んだ際の対応です。
「休職願を出したらどうか」と電話をかけてきたN教頭。さらに、Y先生の担任クラスの保護者会で「担任が弱くて申し訳ない。私がしっかりフォローします」と発言していたことが後に判明します。
6ヶ月後、Y先生は過度のストレスから適応障害と診断され、1か月の休職を余儀なくされました。カウンセリングにお見えになった時には、「15年間大切にしてきた教師としての自信が、たった半年で崩れ去りました」とおっしゃいました。
休職中、彼女は2週間に1回のカウンセリングを継続し、同時に教育委員会の担当者に状況を詳細に説明。客観的に記録していた教頭の言動記録が、彼女の状況説明に大きな説得力を持ちました。
「記録していたことで、『私が思い込んでいるだけ』という自己否定から解放されました。事実として起きていたことだと認識できた瞬間、少し楽になりました」
年度末に異動が認められました。新しい学校では、管理職からの適切なサポートもあり、徐々に教師としての自信を取り戻していきました。
「最初は『また同じことが起きるのでは』という恐怖がありました。でも新しい環境で、少しずつ『私の教育には価値がある』と思えるようになりました」
Y先生は今、異動先の学校で教務主任を任されています。彼女が取り組んでいるのは「教師間支援システム」の構築です。月に一度、教師たちが互いの悩みを匿名で書き出し、それを全員で考える場を設けています。
「辛かった経験から生まれた取り組みです。誰かが苦しんでいても気づかない職場の構造そのものを変えたくて」というY先生。
先日、久しぶりにカウンセリングにお見えになり、「傷は完全には消えていません。でも、その傷が他の誰かを救うかもしれない。そう思えるようになって、私は少し前に進めました」とおっしゃいました。
事例2:ベテラン教師グループからの排除 ― 集団による無言の暴力
Z先生(20代・男性)は教員免許取得後、IT企業で5年間勤務した後に教師の道を選んだ異色の経歴の持ち主でした。デジタル教材の知識や最新の教育トレンドに精通していたZ先生は、赴任した中学校で新しい風を吹き込もうと意気込んでいました。
「最初の職員会議で『タブレットを使った協働学習の可能性』について少し発言したのが、すべての始まりだったと思います」とZ先生は語ります。その学校の英語科は3人のベテラン教師(50代・女性2名、40代男性1名)が強固な結束で長年運営してきました。彼らは伝統的な文法訳読式の指導に強いこだわりを持ち、「これで何十年もやってきた」という自負がありました。
Z先生の新しい提案は、彼らのアイデンティティを脅かすものと受け取られたようです。
排除は巧妙かつ段階的に進行しました。
最初は会議での無視です。Z先生が発言すると、ベテラン教師たちは目を合わせず、意見を取り上げません。会議の後は「今日の話し合いは実りがあったね」と、まるでZ先生がいなかったかのように話します。
次は情報の遮断でした。
「英語科の教材研究会が行われていたことを、終わった後に知りました。『あれ?知らなかった?伝えたはずだけど』と言われましたが、私にだけ連絡がありませんでした」
これが一度ではなく、教材選定、テストの作成、保護者会の準備など、あらゆる局面で繰り返されました。
Z先生が担当するクラスの生徒たちは、彼の双方向型の授業スタイルを楽しんでいましたが、ある日、校内を歩いていると生徒たちがこんな会話をしているのを耳にしました。
「Z先生の授業って楽しいけど、ちゃんと英語力つくのかな?」 「A先生が『大学入試に対応できないから心配』って言ってたよ」
ベテラン教師たちが生徒に対してもZ先生の授業を暗に批判していることが明らかになりました。
最も深刻だったのは、授業研究会での出来事です。Z先生が提案した協働学習の公開授業が決まり、準備を進めていましたが、直前になって他の英語教師たちから「体育祭の準備で忙しいから手伝えない」と言われました。一人で教材準備をし、当日を迎えたZ先生でしたが、授業後の検討会では、
「従来の授業スタイルとかけ離れている」
「生徒が楽しいだけで、学力がつくのか疑問」
「若手だから経験不足なのは仕方ないが…」
という批判が集中し、建設的な意見は一切ありませんでした。
「最も辛かったのは、職員室で自分の机に戻ると、周囲が急に静かになることです。明らかに私のことを話題にしていたのに、私が来ると会話が止まる。その孤立感は言葉では表せません」とZ先生は振り返ります。
3ヶ月後、Z先生は深刻な不眠と胃痛に襲われ、医師からは「このままでは胃潰瘍になる」と警告されました。
この危機感から、Z先生は大きな決断をします。まず、同じ学校の若手理科教師と連携し、互いの授業を参観し合う小さな校内研究会を立ち上げました。「一人じゃないという実感が、何より救いでした」とZ先生は振り返ります。
Z先生は今、教育委員会の指導主事として、主に学校のICT環境整備に関わっています。「決して華々しい逆転劇ではありませんでした」と彼は率直に話します。
「指導主事になっても、しばらくは自信を取り戻せず、夜中に突然あの時の言葉を思い出して眠れなくなることもありました」とZ先生。
変化は緩やかに訪れたと言います。「複数の学校を訪問する中で、少しずつ自分の強みに気づけるようになりました。排除された学校では『変わり者』でしたが、別の環境では『専門性がある』と評価されることもある。環境が人を決めるんだと実感しています」。
彼は今でも教壇に立ちたい気持ちを捨てきれていないと言います。
「でも、以前とは違う形で教育に関われていることには感謝しています。傷は癒えつつありますが、完全に消えることはないでしょうね」
Z先生の表情には明るさが戻りつつあります。
事例3:陰湿な噂の拡散 ― 評判を破壊する見えない毒
A先生(40代・女性)は小学校で16年間担任を務め、温厚な人柄と丁寧な指導で知られていました。昨年度まではトラブルらしいトラブルもなく、学校生活を送ってきました。
変化が訪れたのは、新年度から同学年を担当することになったB先生(30代・女性)が転勤してきてからです。
「最初は普通の同僚関係でした。むしろB先生は明るく社交的で、職員室に新しい活気をもたらしてくれたと思っていました」とA先生は当時を振り返ります。
しかし、学校行事の担当決めで小さな意見の食い違いがあった後から、状況が一変します。
ある日、保護者から連絡帳でこんなメッセージが届きました:「先日お話しした件について、もう少し詳しく相談させてください」。しかし、その保護者と特別な相談をした記憶はありませんでした。
不思議に思って電話で確認すると、その保護者は「B先生から『A先生が子どもたちを怒鳴りつけているので心配』と聞いたので相談したのですが…」と言うのです。
A先生は動揺しました。自分ではそんな指導をした自覚はなく、子どもたちとの関係も良好だったからです。
さらに調査すると、B先生が保護者会終了後に、「A先生のクラスの子どもたちが泣いていた」「感情的な指導が多いので気をつけた方がいい」といった情報を流していたことが判明しました。
「最も驚いたのは、そんな事実がないにもかかわらず、多くの保護者がそれを信じていたことです。長年信頼関係を築いてきたはずなのに、根拠のない噂があっという間に広がっていました」とA先生。
職員室でもA先生に対する風当たりが変わります。「感情的になりやすいから気をつけて」と他の教師から忠告されたり、校長から「保護者対応に気をつけるように」と注意されたりするようになりました。
そして決定的だったのは、学校公開日の出来事です。いつもより多くの保護者が参観に来ており、A先生は通常通り授業を進めていましたが、子どもが間違った答えを言った時に「もう一度考えてみよう」と言っただけで、翌日には「A先生が子どもを否定した」という噂が広がっていました。
「私の言動すべてが誤解される環境になっていました。自分の教室に監視カメラがあるような錯覚さえ覚えました」
調査の結果、B先生は前任校でも同様の「ターゲットを決めて噂を広める」行為を繰り返していたことが分かりました。彼女は自己愛的な承認欲求が強く、他の教師を貶めることで自分の評価を相対的に高めようとする傾向があったのです。
A先生は次第に自信を失い、クラスでの言動にも過度な自己検閲をするようになりました。「何を言っても誤解される」という恐怖から、子どもたちとの自然なコミュニケーションさえ難しくなっていきました。
精神的ストレスは身体症状となって現れ、慢性的な頭痛、不眠、過食と体重増加に悩まされるようになります。カウンセリングに来たA先生は、「教師になって初めて、教室に行くのが怖いと感じました」とA先生は当時の心境を語ります。
転機となったのは、同学年の別のベテラン教師C先生の存在でした。長年A先生の指導を見てきたC先生は、噂の不自然さに気づき、A先生に直接声をかけてくれたのです。
「誰も信じてくれないと思っていた職場で、一人でも味方がいることが分かった瞬間、涙が止まりませんでした」
C先生の協力を得て、A先生は校長に正式な報告書を提出。B先生の前任校での同様の行為も含め、具体的な事実関係が調査されました。同時に、A先生はカウンセリングを受け始め、自分を責めることから少しずつ解放されていきます。
「カウンセリングで『これはモラルハラスメントの典型的なパターンです』と言われたとき、『私が悪いわけじゃないんだ』と初めて思えました」とA先生。
調査の結果、B先生の行為が問題だと認定され、B先生は翌年度に別の学校へ転任することになりました。また、A先生のクラスの保護者会では、教育委員会の担当者も同席し、噂の誤りについて公式に説明が行われました。
「一度広がった噂を完全に消すことはできませんでしたが、少なくとも『これは事実ではない』と公の場で認められたことが、私の救いでした」と、A先生は安堵されました。
A先生は、引き続き同じ学校で教壇に立っています。「完全に元通りとは言えませんが、少なくとも教室に行くのが怖くなくなりました」と彼女は話します。
B先生の転任後、徐々に噂は収束し、保護者との関係も修復されつつあります。「信頼を取り戻すのは、失うより何倍も時間がかかる」と実感しながらも、一日一日を大切に過ごしています。最も変わったのは彼女自身の態度だといいます。
「以前は学校のことを家族にも話せませんでした。『教師は弱音を吐かない』という変な固定観念があって。今は素直に『辛かった』『助けて欲しい』と言えるようになりました」。
彼女は週末に同じ経験をした教師と会って話すこともあるそうです。「特別な活動をしているわけではありませんが、『私だけじゃない』と思えるだけで違います。そして時々、若い先生が悩みを打ち明けてくれることがある。その時は全力で聴く。それが私にできる恩返しです」と、カウンセリングで力強く語ったA先生。その言葉に、私は感激しました。
自己愛型いじめの特徴と対処法
これら3つの事例から見えてくる「自己愛型いじめ」の共通点を見てみましょう。
自己愛型いじめの5つの特徴
- 加害者は自己像にこだわる
N教頭の「熱心な指導者」、ベテラン教師の「伝統的教育の守護者」、B先生の「人気教師」など、自分の理想像を守るためにいじめを正当化します - 批判を受け入れられない
自分の考えや方法に対する異議や変化の提案を深刻な脅威と捉えます - 操作と支配を好む
直接的な攻撃より、情報操作や孤立化など、巧妙な手段を好みます - 集団力学を利用する
他者を巻き込み、自分の行為を「みんなの総意」にすり替えます - 「良い人」の仮面を被る
表向きは親切で協力的に振る舞い、いじめを見えにくくします自分が一番出ないと気が済まないし、それを脅かす相手はどんな手段を使ってでも陥れる卑劣な連中です。
「自己愛型いじめ」からの回復と対処法
1 証拠を残す
日時、場所、言動を客観的に記録する習慣をつけましょう。感情的な評価ではなく、事実を記録することが重要です。Y先生は日記形式で教頭の言動を記録したことで、後に産業医との面談で実態を正確に伝えることができました。
2 同盟者を見つける
完全な孤立は最も危険な状態です。職場内で一人でも理解者を見つけることが重要です。Z先生の場合、同じく若手の理科教師と連携することで、互いに孤立感を和らげることができました。
3. 自己効力感を守る
いじめの最大の害は、自己効力感(自分はできるという感覚)の喪失です。A先生は自分の教育観を文章化し、定期的に読み返すことで自己基準を維持しました。
4. 外部のサポートを得る
学校という閉鎖環境では客観的視点が失われがちです。まずは、管理職への相談が基本ですが、頼りにならない場合もあります。その場合は、都道府県の教育委員会への相談をお勧めします(市町村教育委員会は避けた方が無難です))。
さらに、カウンセラー、医師、弁護士など、外部の専門家に相談することで新たな視点を得られます。
5. 環境変化を厭わない
最終的には異動や転職も選択肢に入れる勇気が必要です。Y先生は休職後、別の学校への異動を願い出て実現。Z先生は教育委員会の研究職への配置転換を勝ち取りました。職場いじめのある環境に留まることが最善とは限りません。
教師のいじめは「構造的問題」である
最後に強調したいのは、教師間のいじめは個人の性格の不一致や相性の問題ではなく、教育現場特有の構造的問題だということです。
閉鎖的な環境、曖昧な評価基準、「和」を重んじる文化、そして疲弊した教師たちが互いを責める悪循環。これらの要素が複合的に作用し、いじめを生み出し、維持しています。
そして何より、侮辱罪、名誉棄損罪に該当する内容であっても管理職は見て見ぬ振り。相談しても、いなす。結果、分限・懲戒処分にもならない。腐りきっている職場は少なくありません。
だからこそ、「あなたが悪いのではない」ということを知ってほしいと思います。そして、一人で抱え込まず、専門家のサポートを求めることが、回復への第一歩となります。
教師としての使命感から「耐えなければ」と思うかもしれませんが、あなたの心身の健康こそが、子どもたちに最高の教育を提供するための土台なのです。
あなたは一人ではありません。そして、必ず道は開けます。