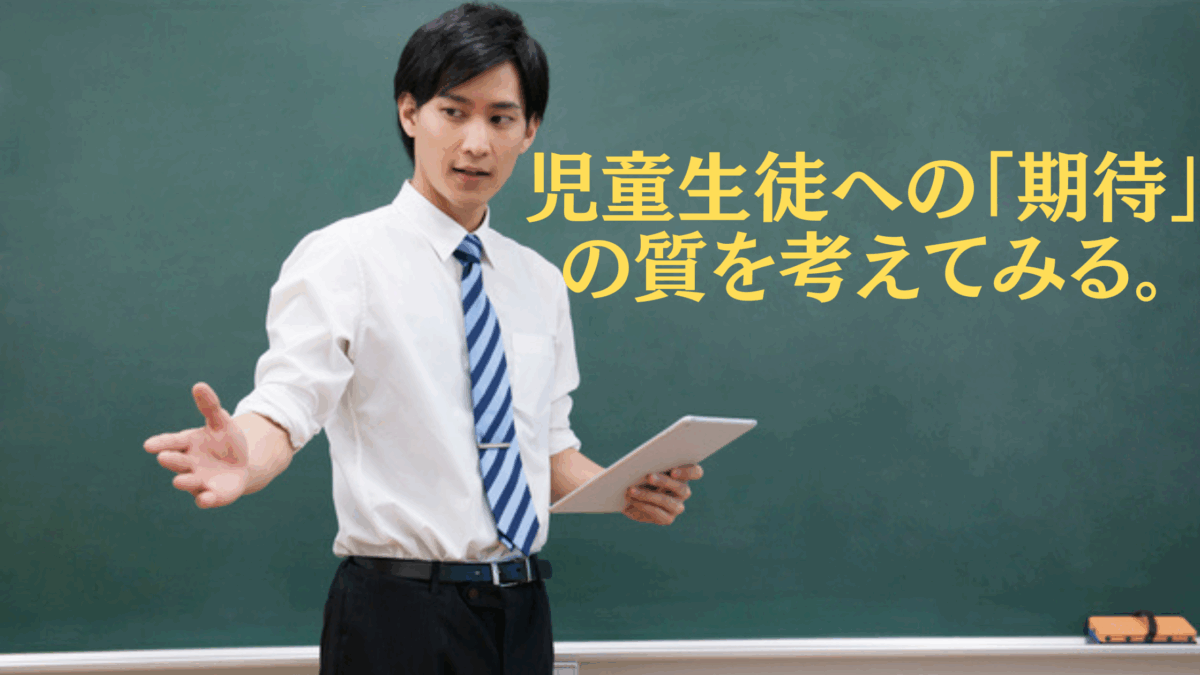目次
教育という希望の営み
教壇に立つ先生方は、常に未来を見つめています。
目の前の子どもたちの中に、明日の可能性を見出し、その芽を育てようとする。それは教師という職業の本質であり、美しさでもあります。
「この子はきっと伸びる」
「次こそ変わってくれるはず」
こうした「期待」は、教育のエンジンとなります。教育心理学ではピグマリオン効果として知られるように、教師の期待は子どもの成長に実際の影響を与えうるのです。教師が信じることで、子どもは本当に変わることがあります。
しかし、教壇に立ち続けるうちに、多くの教師がある深い痛みと向き合うことになります。それは「期待」という名の重荷が、自らと子どもの両方を苦しめていく現実です。
期待は諸刃の剣です。それは希望となって子どもを励ますこともあれば、重圧となって教師と子どもの両方を傷つけることもあります。この微妙なバランスを理解することが、教師としての深い洞察と言えるでしょう。
「期待」が変質する瞬間 — ある中学校教師の葛藤
岸本先生(仮名・45歳)は、中学校で数学を教えて20年のベテラン教師です。熱意あふれる指導で多くの生徒から慕われてきましたが、近年、ある苦しみを抱えるようになりました。
「私の指導法は間違っていないはずなのに、なぜこの子たちは変わらないのだろう」
特に悩ましかったのは、2年生の佐藤君(仮名)との関係でした。数学の基礎的な力はあるものの、やる気が見えず、提出物も遅れがちな生徒です。
岸本先生は佐藤君に特別な関心を持ち、放課後に残って個別指導をし、丁寧な添削を繰り返し、時には厳しく叱ることもありました。
「君には才能があるのに、それを無駄にしているのは本当に残念だ」
「もっと努力すれば、必ず結果はついてくるよ」
しかし、期待した変化は訪れません。むしろ、佐藤君は次第に数学の授業自体から心を閉ざすようになっていきました。
岸本先生の「期待」は、いつしか「善意の強制」に変わっていたと思われます。自分の想像した成長曲線に佐藤君が沿わないことに、岸本先生は個人的な挫折感すら覚えるようになりました。
「これだけ時間をかけているのに、なぜ変わらないのか」
「私の教え方が悪いのだろうか」
「この子のためを思っているのに、なぜ伝わらないのか」
こうした思いは、やがて佐藤君への無意識の圧力となり、二人の関係はさらに硬直していきました。
ある日の職員室での出来事が、岸本先生の心に重くのしかかります。同僚の田中先生が、何気なく漏らした言葉でした。
「岸本先生、佐藤君、最近数学の授業でうつむいてばかりですよね。何かありました?」
その何気ない一言が、岸本先生の胸に刺さりました。佐藤君は他の授業では普通に参加している。問題は数学の授業だけなのです。そして、その原因は、自分の「期待」なのかもしれない。
その夜、岸本先生は自分の教師としてのあり方を深く見つめ直す時間を持ちました。
教師自身の「期待された歴史」が作る罠
なぜ教師はこれほどまでに「期待」に縛られてしまうのでしょうか。
その根には、多くの教師が歩んできた人生の軌跡があります。教師という職業を選ぶ人々の多くは、自らが「優等生」として育ってきた経験を持つことが少なくありません。
「真面目だね」「よく頑張るね」と周囲から認められる喜びを知り、 「期待に応えなさい」というプレッシャーの中で自己価値を形成してきたのです。
岸本先生もまた、そうした一人でした。小学校時代から「将来有望」と言われ続け、努力して結果を出すことが「自分の価値」だと無意識に信じてきました。そして今、教師として佐藤君に接する際、自分が受けてきた「期待」の型をそのまま当てはめていたのです。
岸本先生の自宅には、今でも中学時代の担任だった山田先生(仮名)からの手紙が大切に保管されています。
「岸本君は必ず大きく成長する。その素質と努力を無駄にしないように」
その言葉に励まされて教師になった岸本先生。しかし今、同じような言葉を佐藤君にかけているのに、なぜ同じ効果が生まれないのか。その疑問が、岸本先生の心を深く苦しめていました。
この経験が、無意識のうちに教育観を形作ります。
「頑張れば報われるはず」
「努力は必ず実を結ぶもの」
「期待に応えることが、人としての価値である」
そして、この価値観を持ったまま教壇に立ったとき、子どもたちにも同じレンズを通して接することになるのです。
問題は、この「期待」が「自己価値」と強く結びついてしまうことです。
「子どもが期待通りに成長しないのは、私の教師としての価値が低いからではないか」
「もっと頑張れば、きっと子どもは変わるはず」
こうして、教師は自らを追い込み、同時に子どもたちにも過剰な圧力をかけてしまう悪循環が始まるのです。
岸本先生は改めて気づきました。山田先生の期待は、岸本少年にとって「翼」となりましたが、それは岸本少年自身が「認められたい」「期待に応えたい」という強い内発的動機を持っていたからです。一方、佐藤君にはそれがない。いや、あるのかもしれないが、それは数学以外の分野かもしれないのです。
転機 — 「うまくいかない」を許容する視点への移行
岸本先生の転機は、ある研修会での出会いから始まりました。
年配のスクールカウンセラーの言葉が、彼の心に深く刺さったのです。
「教育とは、『うまくいくことを前提にしない』営みではないでしょうか。植物を育てる庭師は、すべての種が同じように、同じタイミングで芽吹くとは思っていません。教師もまた、同じ視点を持つことが大切です」
この言葉をきっかけに、岸本先生は自分の「期待」のあり方を見つめ直し始めました。
伝えたことがすぐに理解されなくても、当然のことと受け止める。 何度注意しても、すぐに変わらないのは普通のことだと心得る。 変化は、ある日突然現れることもあれば、見えないまま終わることもあると認識する。
この「ズレ」を自然なものとして受け入れる視点が、教師自身の心を守る鎧となります。
「裏切られること」も仕事の一部。 「思い通りにならないこと」が標準状態。
そして、それでも「関わり続ける」ことこそが、教育者の矜持なのです。
この気づきを得た岸本先生は、佐藤君への接し方を変えることにしました。
研修から戻った翌週、岸本先生は佐藤君に何気なく声をかけました。
「佐藤君、最近何か面白いことあった?」
数学の話ではなく、ただ佐藤君という一人の人間に関心を持つ——そんな単純なことから始めてみたのです。佐藤君は最初、戸惑った様子でしたが、少しずつ会話が生まれていきました。
岸本先生はさらに、授業の中でも変化を作り出そうとしました。佐藤君が提出物を持ってきたとき、以前なら「もっとここを頑張れば」と言っていたところを、「君なりの解き方で進められているね」と認めることから始めたのです。
期待を手放したその先に広がる可能性
岸本先生は、佐藤君に対する「期待」の質を変えることにしました。
「佐藤君、数学が好きになってくれたらうれしいけど、今はそうでなくても全然構わないよ。君の中には数学以外にも、きっと大切にしたいものがあるんだろうね」
驚いたことに、この「期待の軽減」が、二人の関係性に変化をもたらしました。重圧から解放された佐藤君は、少しずつ本音を話すようになります。
「実は、数学自体は嫌いじゃないんです。でも、期待されるのが怖かった。前の学校でも、できると思われてプレッシャーをかけられて…。失敗するのが怖くて、最初からやらないほうが楽だったんです」
皮肉なことに、教師が「期待」という荷を下ろしたとき、佐藤君は自由に、自発的に動き始めたのです。
教師の「こうあってほしい」という思いが強すぎると、子どもたちは「期待に応える自分」を演じることに疲れ果てます。あるいは、その重圧に反発して、あえて逆の道を選ぶこともあります。
しかし、「そのままでいい」「無理に変わる必要はない」と伝えられたとき、子どもたちははじめて「自分の意思で変わる」自由を手に入れるのです。
期待を手放すことは、子どもを見捨てることではありません。 むしろ、子どもの内側にある成長の力を信じるという、最も深い信頼の形なのです。
佐藤君との関係に変化が訪れたのは、それから約1か月後のことでした。ある日、佐藤君が自分から質問しに来たのです。それまで、放課後に残って勉強するのは岸本先生の「指示」でしたが、この日は佐藤君自身の意思でした。
「先生、この問題、もう一度説明してもらえませんか?自分でやってみたんですけど、どうしても分からなくて…」
岸本先生は、佐藤君の中に生まれた「学びたい」という内発的動機の芽を大切に育もうと思いました。「期待」という名の重荷を降ろしたことで、本当の意味での教育関係が始まったのです。
子どもの成長を「待つ」という教育技術 — 小学校教師の実践から
小学校で12年のキャリアを持つ村田先生(仮名・30代)は、「待つ」という教育技術を大切にしています。
村田先生が担任になった4年生のクラスには、授業中に落ち着きがなく、周囲の児童とトラブルを起こす池田君(仮名)がいました。周囲の教師からは「もっと厳しく指導すべきだ」という声もありましたが、村田先生は異なるアプローチを選びました。
「私は池田君に『変わること』を期待していません。ただ、彼のありのままを受け止め、彼自身が自分で選択できる余地を作ることを心がけています」
村田先生は、池田君が落ち着かないときに「静かにしなさい」と叱るのではなく、「今は動きたい気持ちなのかな?少し廊下で深呼吸してくるといいよ」と声をかけるようにしました。これは「問題行動」への対処ではなく、池田君自身の内側の感覚に寄り添う関わりです。
さらに、クラス全体にも「一人ひとり違って当たり前」という価値観を伝え続けました。「みんな同じようにできなくていい。大切なのは、自分がどう感じて、どんな選択をするかだよ」という言葉を繰り返したのです。
一ヶ月経ち、二ヶ月経ち…。すぐに劇的な変化は見られませんでした。しかし、半年が過ぎた頃、少しずつ池田君に変化が現れ始めます。自分から「ちょっと気持ちが落ち着かないから、外に出てきていい?」と言えるようになったのです。これは、自己認識と自己調整の力が育ってきた証拠でした。
村田先生はこう振り返ります。
「成長には時間がかかります。特に、情緒や社会性の発達は、まるで目に見えない氷山の下の部分のようなもの。表面に現れるのはずっと後のことなのです。だから、目に見える変化を早急に期待するのではなく、目に見えない内面の育ちを信じて『待つ』ことが大切なのだと思います」
村田先生の実践から学べるのは、「期待」とは、「あるべき姿に早く到達してほしい」という焦りではなく、「あなたの中には成長する力がある」という信頼であるということです。そして、その信頼を持ちながら「待つ」という姿勢こそが、真の意味での教育的期待なのです。
現場で実践できる「期待」との向き合い方
教師が自分の「期待」と健全に向き合うための具体的なアプローチをご紹介します。
1. 自分の「期待パターン」を知る
まずは自己観察から始めましょう。子どもの言動に対して、どのような場面で強い期待や失望を感じるのか、パターンを見つけることが大切です。
実践例: 教師専用の「期待日記」をつけてみましょう。「今日、どの場面で強く期待したか」「その期待はどこから来ているのか」を短く記録します。この習慣を通して、自分の期待パターンが見えてきます。
例えば、ある高校の先生は次のような記録をつけることで、自分の「期待の歪み」に気づいたと言います。
「今日、Aさんの英語のテスト結果に強い失望を感じた。前回90点だったのに、今回は75点。なぜこんなに下がったのかと問い詰めてしまった。振り返ると、山田さんに私は特別な期待を抱いている。それは彼女の能力というより、彼女が『私の教え方の証明』になってほしいという思いからかもしれない。」
このような自己観察を続けることで、「子どものため」と思っていた期待が、実は「自分のため」の期待だったことに気づくことがあります。
2. 「期待」と「願い」を区別する
「期待」が重荷になるのは、それが「こうあるべき」という強制を含むからです。これを「願い」という柔らかさに変換する練習をしましょう。
実践例: 「〇〇すべきだ」という言葉が心に浮かんだら、意識的に「〇〇だといいな」に言い換えてみましょう。言葉の選び方一つで、子どもへの圧力も、自分自身へのプレッシャーも軽減できます。
中学校の国語教師のB先生は、この「言い換え」の効果をこう語ります。
「以前は『君は作文をもっと上手に書けるはずだ』と言っていましたが、今は『君の考えをもっと知りたいな』と伝えるようにしています。すると不思議なことに、子どもたちの表情が変わるのです。『できなければならない』という重圧ではなく、『自分の考えに興味を持ってくれている』という安心感が生まれるようです。」
この小さな言葉の変化は、教師自身の心の持ち方も変えていきます。
3. 「成長の多様性」を認める視点を育てる
すべての子どもが同じペース、同じ方向で成長するわけではありません。多様な成長の形を認められるよう、視野を広げることが大切です。
実践例: 「一人の子どもを多角的に見る」習慣をつけましょう。問題を抱える子どもでも、別の場面では生き生きとしている瞬間があるはずです。そうした多面性に目を向けることで、一元的な「期待」から解放されていきます。
ある特別支援学級のC先生は、「成長の多様性」をこのように実践しています。
「私のクラスの子どもたちは、学習面では苦戦することが多いです。でも、私は毎日『今日の輝き』というノートをつけています。例えば『今日、田中君は給食の配膳を手伝ってくれた。周りへの気配りができるようになっている』など、学習以外の場面での成長や輝きを記録するのです。このノートが、私の『期待』を多角化してくれます。」
子どもの多様な側面に目を向けることで、教師の「期待」も柔軟になり、一つの側面でのつまずきに一喜一憂しなくなるのです。
4. 「時間軸」を長く取る
教育の成果は、すぐには見えないことが多いものです。時間軸を短く取りすぎると、期待と現実のギャップに苦しむことになります。
実践例: 「今ではなく、10年後の姿」を想像する習慣をつけましょう。目の前の子どもの未熟さに焦るのではなく、「今は途上にある」という長い目で見る視点が、教師自身の心の安定をもたらします。
35年の教師経験をもつベテランのC先生はこう語ります。
「若い頃は、目の前の変化ばかりを求めていました。でも今は、教え子が大人になって『あの時の先生の言葉が、今になって分かります』と言ってくれることが、最大の喜びです。教育の果実は、10年、20年の時を経て実ることもある。そう思えるようになると、日々の小さな変化に一喜一憂せず、長い目で子どもたちを見守れるようになりました。」
時間軸を広げることで、教師の「期待」はより余裕を持ったものになります。目の前の結果だけでなく、見えない未来にもつながっているという認識が、教師自身の心の安定をもたらすのです。
「期待」の質を問い直す — より健全な教育観へ
教師という職業に、期待はつきものです。それを完全に排除することは、教育の本質を失うことにもなりかねません。
大切なのは、「期待」の”量”ではなく、その”質”を見直すことです。
「自分の思い通りになってほしい」という執着型の期待から、 「あなたらしく、あなたのペースで成長していく」ことを見守る解放型の期待へ。
その子が変わるかどうかは分かりません。 それでも、変わる力を持っていると信じます。
裏切られるかもしれません。 それでも、関わり続けます。
このような揺るぎないスタンスを持つとき、教師は自らを苦しめる「期待」の重荷から解放され、より深い次元での教育関係を築いていくことができるでしょう。
そして、そのような教師との出会いこそが、子どもたちの人生に長く残る貴重な財産となるはずです。
長年教師を続ける中で、期待との向き合い方が変わったという50代の先生は、こう語ります。
「若い頃は『この子をこう変えよう』という思いが強かった。でも今は『この子のそばにいよう』という思いの方が強いです。期待するというより、ただそばにいて見守る。それがかえって子どもの自発的な変化を生み出すことを、経験から学びました。」
教師として自らを守るためのメンタルケア
「期待」の質を変えることは、子どものためだけでなく、教師自身のメンタルヘルスにとっても重要です。期待の重圧は、教師自身を疲弊させ、燃え尽き症候群の要因にもなります。
1. 「完璧な教師」という幻想から自由になる
多くの教師は「完璧であるべき」という無意識の思い込みを持っています。しかし、教育という営みに完璧はありません。むしろ、教師自身の弱さや失敗を認められることが、子どもたちへの真の教育になることもあります。
中学校教師のE先生はこう振り返ります。
「クラスでミスをしたとき、以前は取り繕っていました。でも今は『先生も間違えることがあるね。ごめんね』と素直に認めるようにしています。すると子どもたちも『失敗してもいいんだ』と思えるようになるのです。」
完璧を目指すのではなく「十分に良い教師」でいることを許す。この自己許容が、教師自身を過剰な期待から守ってくれます。
2. 同僚との対話で「期待」を相対化する
自分の「期待」が適切かどうかは、一人で判断するのが難しいものです。同僚との対話を通して、自分の期待のあり方を客観的に見つめ直す機会を持ちましょう。
「私、この子に対して期待しすぎかもしれない」 「この子への関わり方で悩んでいるんだけど、どう思う?」
このような素直な対話が、教師自身の視野を広げ、期待の歪みを修正する助けになります。
3. 「成功体験」ではなく「関わり体験」を大切にする
教師の喜びを「子どもの変化」や「成功」だけに求めると、期待のハードルが上がりすぎてしまいます。むしろ「関わりそのもの」に価値を見出すマインドセットを育てましょう。
「今日も子どもたちと過ごせた」 「あの子の話をじっくり聞くことができた」 「新しい発見があった」
こうした日々の小さな「関わり」そのものに意味を見出せる視点があれば、「結果」への執着が減り、より余裕を持って教育に向き合えるようになります。
教師として成長するための内省の問い
教室に立ち、子どもたちの姿を眺めながら、ご自身の心に浮かぶ言葉に耳を澄ませてみてください。
「もっとできるはず」「なぜ変わらないのか」というフレーズが響くなら、それは「執着型」の期待かもしれません。
一方、「あなたのペースでいい」「今のあなたを受け入れる」という言葉が聞こえるなら、それは「解放型」の期待でしょう。
どちらの声が大きいでしょうか。 どちらの声を育てたいでしょうか。
教師自身が自分の内なる声に耳を澄まし、自らの「期待」の質を見つめ直すとき、真の教育者としての成長が始まるのではないでしょうか。
「期待」という名の荷物を、少し軽くしてみましょう。 そして、より自由な心で、子どもたちとの関わりを味わってみましょう。
それが、教師自身の心を守り、本来の教育の喜びを取り戻す第一歩となるはずです。
最後に付け加えたいのは、私が現職時代に先輩教師が話してくださった言葉です。
「教師が本当に学ぶべきなのは、期待というエネルギーの向き先だ。子どもを『変えよう』とする期待ではなく、子どもの『存在そのもの』を喜ぶ期待。そこには評価も条件もない。ただ『あなたが今日もここにいてくれて、本当に嬉しい』と心から思える教師だけが、子どもの心の扉を開く鍵を持っているんだよ。」
この言葉には深い真実があります。期待は方向性を変えれば、重荷ではなく、教師も子どもも解放する光になるのではないでしょうか。